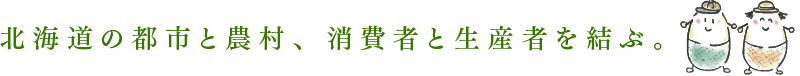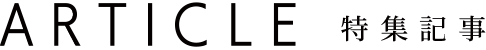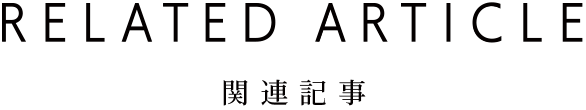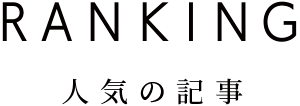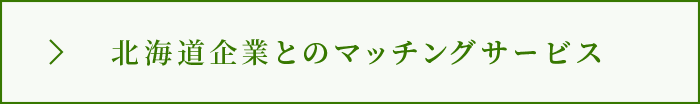国内の林業が勢いを取り戻し、国産木材のニーズが上向いています。特に、森林面積の広大な北海道に注目が集まっていますが、一方では、他の業界同様に後継者不足などの課題も抱えている現状と課題について、(一社)北海道造林協会会長で蘭越町長の金秀行(こんひでゆき)さんにお話を聞きました。 (聞き手・文/伊藤孝)
―本道の造林事業の現状を教えて下さい。
現在、北海道の人工林は成熟期を迎えており、道産木材のカラマツは国内でも買い手が増え、伐採後の着実な再造林がますます重要になっています。森林整備にも様々な部分で繋がっていきますので、ここをきちっと進めることが当協会に求められています。
民有林の伐採後、森林組合にも委託して森林整備計画を実施していく過程で、所有者の方たちに「もっと森林を整備しましょう」と呼びかけるわけですが、どうしても個人負担が多くなると大変ですので、そうした部分に森林環境税を上乗せして、所有者の負担を軽減することもできます。
伐採後の再造林には、伐って植えて育てて使う、このサイクルを進めていかなければなりません。そのために今、クリーンラーチ(カラマツとグイマツの交配品種)が注目されています。まだ時間を要しますが、生長が速く、材密度が高くて強度があり、CO2の固定能力に優れ、野ネズミの食害を受けにくいため、道産木材の新しいエースと目されています。
全国的にも、スギに替わる新たな樹種を育てようとしていますが、これから林業に占める北海道の役割はもっと重要になってくると思います。そういう意味で、今、国の予算のうち森林予算は順調に増えています。

(一社)北海道造林協会会長 金 秀行 さん
―戦後に植樹した木がちょうど今、木材向けサイズに生長していますね。
そうです。しかし、人工林を伐採して次々と木材にして、そのまま放置しておけば森林は消滅してしまいます。だからこそ造林事業を継続し、繰り返していかなければならないんです。
おかげさまで、造林協会の会員には、種苗から苗木を作る方たちと、それを買って植えて育てる森林組合とがいますので、当協会では、苗木つくりと植樹後の下刈り、間伐、除草などを併せて進めています。
苗木の作り手は一時より少なくなりましたので、当協会では育成も考えていかなければなりません。
また、価格一つ決めるにしても、人件費や燃料費の高騰で、作り手は少しでも苗木を高く売りたい、しかしそれを買って植える側は、やはり安いほどありがたい。ですから当協会には苗木検討委員会があり、双方の意見を聞いて調整し、合意形成を図りながら整備を進めていくのも役割の一つです。
植える側としても、改良して、病気に強い苗木、たとえば先ほどのクリーンラーチを増やすようにしていけば、北海道の木材需要もまだまだ高まっていくと思いますね。
―林業の担い手育成については。
非常に重要です。だからこそ旭川の道立北の森づくり専門学院のような優れた教育施設の重要性も増していくわけですが、現実には、入学者が定員に達していないので、もっと世間に知ってもらうと同時に、林業関連業者の方からも、学院に人を送り出すやり方が必要です。当協会も、学院をPRしながら後継者対策を進めていくのが役割の一つだと考えています。
学院の卒業生は、就職率も高いですし、業界が欲しがる人材です。だからこそ、入学を促す仕組みを業界が皆で広げていくべきですし、これからは林業も、賃金の安定化は必須条件なので、通年の雇用体系を構築して事業を行っていくことが必要だと思います。
また逆に、林業業界で働いた経験がある人、関連企業の社員の人などを、さらにステップアップさせる機関として送り出すという道もあると思います。実際に森林環境税の使い道の中にも担い手対策があるわけですから、そうしたやり方も可能なはずです。

―北海道林業の今後の課題と可能性は。
やはり担い手対策は今後ますます重要になります。将来的に人口は増えませんから、その中でいかに効率よく仕事ができる技術を持った人を作業に充てるかが重要になってきます。当然、その人たちの労働環境は、今後より一層きちんと整えていかなければいけません。優れた技術を持った人が効率よく働くことができて、一緒に働く人たちと職場環境を良くしていけば、林業はますます伸びていくと思います。
これから環境問題などを考えていく上で、森林の果たす役割はすごく大きい。CO2をゼロにするのは不可能ですから、ただ減らすだけではなく、木を育てて“吸収” させ、“固定” させることを併せて考えていかなければ駄目です。そうした部分を色々な場所でPRしていき、皆さんが持っている森林をどう有効活用するかという部分がこれからはもっと必要になると思います。
日本において、森林の果たす役割は永遠です。環境も含めて無くてはならないもので、きちんと森林整備していかなければなりません。そこで働く担い手、さらには国や道、それを支える機械力なども連携しながら進めていけば、北海道の森林が果たす役割はますます重要になっていくと思います。だからこそ森林で、林業で働く大切さを子どものうちから教えていくことも大きな意義があることだと思います。