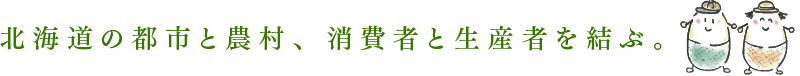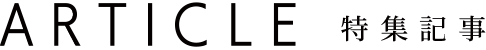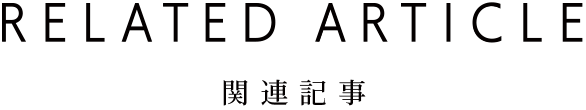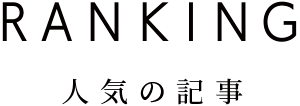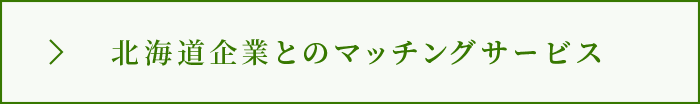米の価格に変化の兆しが見え始めたがまだ店頭の値札までは伝わってこない。米離れは確実に広がったが、北海道米を押してきた本紙としては真面目に働いてきた生産者が幸福感で一日の仕事を終える世界の実現を願う。今こそ、つくる・うる・かうに地域共同体の理念を持って連帯を呼びかけたい。
米の値段が高いまた高くなっている
昨年は米不足状態で推移し、結局出来秋になっても不足気味に推移した。今年は昨年のような品薄感はないが、価格の高騰が続く。米購入に二年連続で嫌なイメージが付き纏う。昨年は店頭に米が並ぶとたちまち買われていったが今年は高値の付いた値札のまま棚には5㎏の米袋がそのままある。
日本産米の足元がぐらついている。消費者は数量や価格に対する疑問が解けずにいる。政府の話はいつも「こうなる」という予想を外すし、生産者団体や中間卸会社も事情説明もない。だからてんでバラバラに消費者は憶測している。
家庭の取り置き分(家庭内備蓄)も結構あるらしい。長い期間放置すると、「米にはコクゾウムシが付きやすいから気を付けるように」と生産者が教えてくれた。黒色のゾウのように長い形をした口が特徴とか。
さて、「値段が高い」、「また米が高くなった」で消費者の米離れも加速している。店頭にはとうとう外国産米も売られるようになった。合計21万t放出した非常用備蓄米は何処に行ったのか、結局「売り場まで回って来ない」状態だ。政府の予想した「落ち着いた値段になる」状況には到底ならないどころか、値上がりさえ止まらず状態だ(15週連続値上がり・4月22日現在)。どうやら卸業者の段階で滞っているみたいで、政府も今度は間髪を入れず7月まで毎月備蓄米を放出すると発表せざるを得なくなった。
農水の昨年の6月発言が悔やまれる。

日本の稲の研究は世界の最先端を行く。これほど旨さの飽くなき探求を続けた国はあったでしょうか。守りたい、日本人の米作りの知恵。
「高騰は続いているが、秋には新米が出る。今備蓄米を放出したら、農家収入に打撃を与える」といって結局備蓄米は出さず仕舞い。これにより国は静観すると決めつけられ、米が投機の対象となっていく。普段米を扱わない事業者までもが米を求め出した。現在がその只中にある。
TVのニュース番組でまだ水を張ってない田んぼ予定地で、生産者と民間業者が話し合い、区画ごと買取る話が決まっていく、いわゆる米の先物買いだ。春の段階で行き先が決まっていくと、秋、消費者には米が求めにくくなるのではないか、筆者はそんな気がする。
米は700%の高関税だ日本の過去の発言を利用
ここにきて日米関税交渉(4月17日交渉スタート)も始まった。これに先立ち、トランプ大統領曰く、「日本は米の関税は700%だ」とやり玉にあげ、「米が不足しているならアメリカ米を輸入せよと言い出す始末だ。
トランプ大統領は間違った認識は毎度のことだが、今回はちょっと勝手が違った。「700%」は実際に日本政府の過去の発言だった。2005年のWTO交渉時の国際相場は「米1㎏44円弱」だったから「778%」と算出し、農水省は「100円の米が877円になる」と発言した。いい加減な発言をした分、大きく跳ね返ってきた。
さらに、2009年の相場では「1㎏122円」だから「280%」になると再計算し、過去の発言「700%」を軌道修正した。論拠のない大袈裟な発言だったが、今その逆襲をトランプ大統領から受けている。もう誤魔化しや不要なパーフォーマンスは抜きでやりたいもの。国民もそれに惑わされてしまう。
「お米や〜い」、「お米の勉強」に読者の反応届く
読者から来たはがきを見てまず感じるのは最大の関心事は「お米の値段」。その中で、実家が米農家のSSさんは『値上がりした分が生産者にあまり還元していない気がします。そもそも生産調整をしているのだから、足りないに決まっていると思います』と、クールなご意見も。
札幌のTYさんは「お米の生産量が全国2位だというのにどうしてこういうことになるのだろう」と素朴な意見。昼はご飯から違うものにチェンジした方(札幌のSYさん)、休日の昼は麺類にという家も。確実に米離れが進んでいる(三笠のWMさんほか)というご家庭も結構ありました。『弁当を作るからお米は必須』(鹿追のNHさん)という方も。
ドキリとするはがきもあった。ある地方都市のSNさんから『昨年、ある味噌屋さんの麹が国産米からアメリカ産の米麹で作られていました。国産のほうが安心です』。これと同じケースは筆者も聞き及んでいて、ある醸造会社は数年かけてじっくり熟成が売りで、高い原料費の上すぐに売り上げにつながらない分、経営が大変とこぼしていた、と又聞きした。ただ、ここは外国産に切り替えていないから余計厳しい。
このように、米を作る側、加工する側、食べる側のすべての現実は大変な状況にある。今こそ『つくる、うる、かうに地域共同体の理念をもって連帯する』気概が必要ではないか、重複する意見の読者は多かったけれど悩みはみな同じだ。皆が安心のできる郷土にしたい。
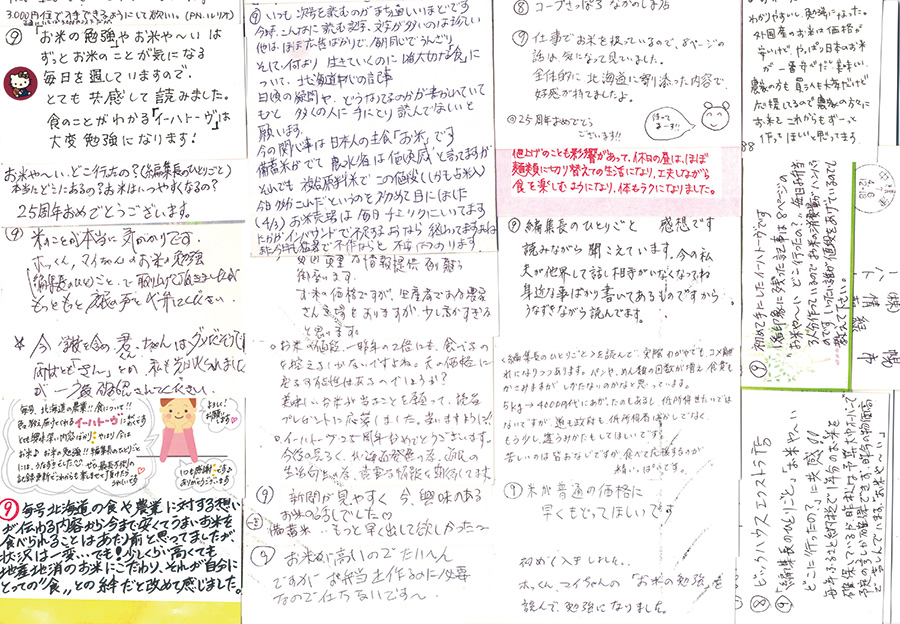
読者からのお米について切実な声が編集室に届けられる、写真はごく一部です。

いにしえから続く日本人のソウルフードは「おにぎり」。
混ぜモノがない分米の食感、食味がストレートに味わえる。まさに、ごまかしが利かない食べ方だ。
厄介米の時代もあった!〝なにくそ作ってやる〞
北海道の稲作にはこれまで数々の障害があった。
開拓時代、「米は寒冷地には無理だから作ってはならぬ」の作付け厳禁作物だった。ところが中山久蔵(現在は北広島市)はひそかに赤毛種を栽培し、成功させた。すると、「待っていました」とでもいうように堰を切ったようにみんなが稲づくりを始めた。まさに「為せば成る」。しかし、しょっちゅう冷害に遭遇するが、寒冷地に強い品種の研究に力が入る。
収穫はできたものの食味が劣悪だった、そう「北海道の厄介米」と言われ続けた。米が食管法でガードされている時代まではそれでも何とかお金になったが、消費者に選択されて食べてもらう時代には厳しかった。
農試での研究が続いた。何年にもわたって遺伝子を掛け合わせて耐寒性のいい、かつ食味の優れた品種を生み出す、これの繰り返しだ。国と道の農試があるが、傍では目立たないが縁の下の力持ち、北海道米躍進の影に彼らのただならぬ研究の成果だ。一つの事例だが、優良品種「ほしのゆめ」は道立旭川農業試験場で8年の歳月をかけて開発された。一つの結果を出すのに数年もかける根気のいる現場、それが農試だ。彼らの働きに拍手喝采だ。
世界中で愛される日本食、その必須は間違いなく万人が絶賛する日本の米だ。高値ゲームにしてはいけない。真摯に世代に繋がる努力をしなければならない。筆者はひたむきに頑張る農家がある限り応援したい。
(山田)